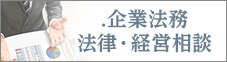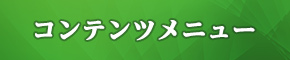相続の基礎知識
Contents
相続の基礎知識 相続を”イチ”から知りたい方へ
- 相続ってどこから手をつけたらよいの?
- 遺産分割ってどうやったらいいの?
- 相続税ってどれくらいかかるんだ?
- 銀行口座解約や生命保険の受け取り方法は?
- 相続財産に多額の借金があることが判明した!
- 揉めないようにしっかりと遺言書を残したい


はじめての相続

相続に関する問題は、初めて経験される方が多いと思います。また、遺産分割は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。複雑で専門知識が必要となる場合がございますが、ひとつひとつ正確に進めなければ、 また一からやり直さなければならいということにもなりかねません。
ただ、逆に言えば、正確にやりさえすれば、関係する方々にも、法律的にも問題のない相続になります。
相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。相続によって受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。また、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が「相続人」と呼ばれます。
相続・遺産分割の進め方
実際に、相続・遺産分割を進めるにあたっては、以下をきちんと調べる必要があります。
間違い・抜け漏れがあれば最初からすべてやり直しになってしまうこともあります。
- 誰が相続人にあたるのか
- 財産がどれだけあるのか
- 遺言は残されているか
- 財産をどのように分けるか
- 相続税は発生するのか
相続に慣れている方はいません。
ご不明点がある場合や、トラブルが想定される場合は、個別の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。
相続方法の決定
相続財産には、現金や不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます(※)。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。
相続するかしないか?その方法は3種類あります。
⑴ 単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合、その借金を債権者に支払わなければいけません。
⑵ 相続放棄
被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、各人が相続放棄をする必要があります。
⑶ 限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続できる財産
相続人は、被相続人の相続財産について、資産も負債もすべて相続できる権利があります。
相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えても結構です。
ですが、財産のなかには相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。
また、相続財産はプラスのもののほかにマイナスのものも含まれます。
プラスの財産
- 不動産(土地・建物)
- 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
- 不動産上の権利
- 借地権・地上権・定期借地権など
- 金融資産
- 現金・現預金・有価証券・株式・国債・社債など
- 動産
- 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
- その他
- 債権・貸付金・売掛金・手形債権・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
- 借金
- 借入金・買掛金・手形債務・リース未払金など
- 公租公課
- 未払いの所得税・住民税・固定資産税など
- 保証債務
- その他
- 未払い費用・未払い利息・未払いの医療費・預かり敷金
- 身元保証など保障額に期間や制限のない保証債務
- 生命保険金請求権
- 死亡退職金
- 香典
相続財産に該当しないもの
上記のような相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられますから、注意が必要です。
親族が亡くなった後にすべきこととは?

親族の方の死は想像したくないものですが、人生の中で誰もが必ず経験する出来事です。残された遺族は、悲しみの中で葬儀や各種手続きをする必要が出てきますが、慣れない手続きで、混乱することも多いと思います。そこで、あらかじめ、身近な方が亡くなった場合に慌てないよう、どのような手続きをする必要があるのかを把握しておくことが重要です。
なお、以下で説明する手続きは、親族が亡くなった場合に、一般的に必要となる手続きであり、具体的にどのような手続きが必要となるかは、亡くなった方の状況により異なります。
亡くなった直後に行うこと(1週間以内)
故人の死後、1週間以内に行うべき手続きは次のとおりです。
死亡診断書の取得
死亡診断書は、病院や介護施設に備えられており、医師が故人の死亡を確認して作成し、遺族に発行します。死亡診断書がなければ、死亡届の取得やその後の手続きも行うことができなくなるので、迅速に取得する必要があります。
死亡届の提出
死亡届は、故人が死亡した日または死亡を知った日から7日以内に提出しなければならないとされています。死亡届の用紙は市区町村の役所で取得することができ、故人の死亡地または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村役場に提出をします。
火葬許可証の取得
火葬許可証申請書は、故人の遺体を火葬するために必要な書類です。通常、市町村役場に「死亡届」と同時に提出します。
会社の健康保険の資格喪失届(会社員の場合)
故人が会社員であり、会社の健康保険に加入している場合、事業主は、死亡日から5日以内に、年金事務所に健康保険・厚生年金保険者資格喪失届等を提出しなければなりません。手続きがスムーズに行われるように、会社に対しても、速やかに、死亡の事実を伝える必要があります。
早めに行うべきこと(1ヶ月以内)
故人の死後、1ヶ月以内に行うべき手続きは次のとおりです。

世帯主変更届の提出(14日以内)
故人が住民票上の世帯主である場合、市町村役場に対し、世帯主変更届を提出する必要があります。
国民健康保険資格喪失届の提出(14日以内)
故人が国民健康保険に加入している場合、市町村役場に対し、国民健康保険資格喪失届を提出し、保険証を返却する必要があります。なお、市町村によっては死亡届を提出することで、国民健康保険資格喪失届の提出が不要になるところもありますので、詳細は提出先にご確認ください。
介護保険資格喪失届の提出(14日以内)
介護保険に加入していた人が亡くなった場合には、故人の住民票のある市町村役場に対し、介護保険資格喪失届等を提出する必要がある場合があります。
国民年金・厚生年金の受給停止手続きを行う(14日以内(厚生年金は10日以内))
公的年金を受給している人が亡くなった場合、年金受給権者死亡届の提出など、年金の受給停止手続きが必要となります。国民年金・厚生年金の受給停止手続きは、市町村役場ではなく、年金事務所や年金相談センターで行うものなので、注意が必要です。
また、法律で期限が定められているわけではありませんが、公共料金の契約変更や解約についても早めに行う必要があるでしょう。
少し落ち着いてからやること(3~4ヶ月以内)
故人の死後、半年以内を目途に行うべき手続きは次のとおりです。

遺言、相続人・相続財産の調査
故人の財産を相続するかどうかを判断するために、故人が生前有していた財産関係について確認をすることが重要です。故人が遺言を作成していた場合には、遺言の内容を早めに確認することが重要です。特に、故人が作成した遺言が自筆証書遺言(故人が手書きで作成した遺言)の場合、家庭裁判所で検認の手続を行う必要があります。
相続放棄(3か月以内)
故人の財産よりも債務の方が大きい場合、相続放棄を検討すべきです。相続放棄は、原則として故人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、注意が必要です。
準確定申告(4か月以内)
確定申告をしなければならない人が亡くなった場合、相続人などが被相続人の名義で所得税の申告を税務署へ行わなければなりません。これが、準確定申告です。所得税は、その年の1月1日から12月31日までの課税所得に対してかかる税金であり、確定申告が必要な人が亡くなった場合、1月1日から亡くなるまでの分の所得税を申告することとなります。特に、自営業者、賃貸物件の大家、年間収入2000万円以上の給与所得者、2か所以上から給与を得ている人、一定の公的年金を得ている人などが亡くなった場合には注意が必要です。
忘れずにやること
故人の死後、期限まで余裕があるからといって忘れてはいけない手続きは次のとおりです。

遺産分割協議
故人の相続財産の調査と並行して、相続財産をどのように分割するかを決める、遺産分割協議を相続人間で進めることも必要です。ここで、遺産分割の内容が決まれば遺産分割協議書を作成します。相続人間で分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて、調停手続を行う必要が出てきます。必要に応じて、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
相続税の申告(10か月以内)
また、故人の相続財産の金額が一定の金額を超える場合、遺産分割により相続財産を取得した相続人は、故人が亡くなってから10か月以内に、相続税の納付をしなければなりません。相続税の申告は、これを忘れると、無申告加算税や延滞税が発生するので注意が必要です。10ヶ月以内に遺産分割協議が成立しない場合でも、暫定的に法定相続分に応じた相続税を納付することも検討すべきでしょう。
お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付