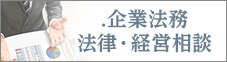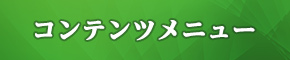【遺留分】遺留分減殺請求権を行使し受遺者から十分な代償金を受け取った事例
事案の概要
| 被相続人 | 母 |
|---|---|
| 相続人 | 養子A、実子B,C,D,E |
被相続人は、生前に自筆証書遺言により被相続人名義の不動産を「同居していた養子(A)と実子である娘(B)に渡す」としていました。 このため、被相続人死亡後に検認の申し立てがなされ、他の相続人C、D、Eがこの遺言を知ることになりました。
解決に至るまで
AとBは夫婦であり、被相続人と生活を共にしていました。したがって「被相続人の介護をしていたのだからこの遺言は当然である」と主張しました。
この主張を発端とし、ABとCDEとの間で感情的な対立が生じてしまい、それ以上の協議が困難となってしまいました。
ところで、被相続人の残した遺言は不動産について明記した1通のほか、預金について明記した2通目がありました。
この遺言には「被相続人の預金は残るC、D、Eへ渡す」いう内容が記されていましたが、その預金の残高は殆ど残っておらず、預金の行方についてAとBから納得のいく説明はありませんでした。
そこでC、D、Eは減殺請求の通知をしたうえ、当事務所に相談をしました。
当事務所は受任後、家庭裁判所へ調停を申し立てました。この中で ⑴ 被相続人の不動産の時価は約5000万と判明した。従ってC、D、Eがそれぞれ受領を主張できる金額は約500万程度相当である。 ⑵ 被相続人が死亡する前、A、Bに対して自宅の建設費用として大金が渡されていた。ということがわかってきましたが、AB側からは現在金融資産がないことを理由に極めて低額な提案がなされるばかりでした。
また、AB側は「C、D、Eも相続人から資産を受け取ったことがある」と主張しましたが、証拠がなく主張は撤回となりました。
このような調停を数回行う中、当事務所はAB側に対し、「調停が不調となり訴訟となると、AB側に不利益な判断をされる」旨を説明し、調停外でも書面や電話により説得したところ、最終的にAB側は「残された不動産の一部を売却してC、D、Eに代償金を支払う」和解に応じました。
C、D、Eの受け取った金額は1人当たり800万円弱であり、穏当な結論となりました。
解決のポイント
1. 調停委員による説得も限界があるので、弁護士からも調停外でも相手方を根気強く説得し、最終的に相手方が説得に応じた形の調停を成立できた。
2. 被相続人が死亡する以前に受遺者に対し渡した資産も、諦めず追及することで遺留分を請求することができる。
お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付